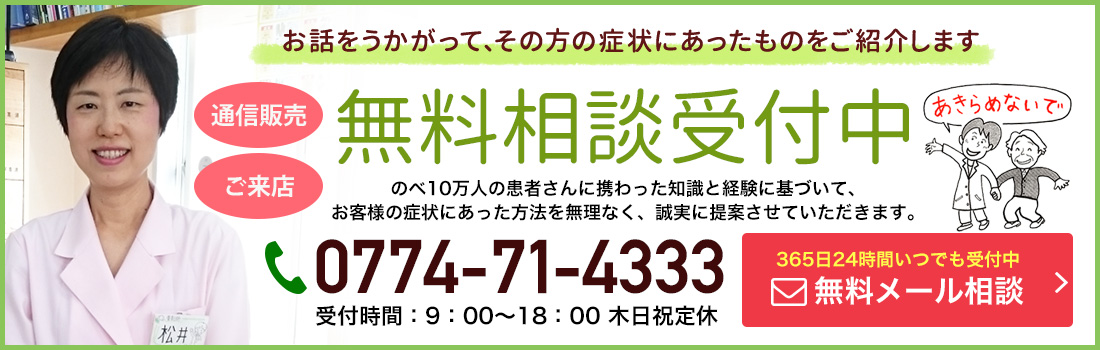パーキンソン病・パーキンソン症候群
はじめに
「パーキンソン病です」と診断されたとき、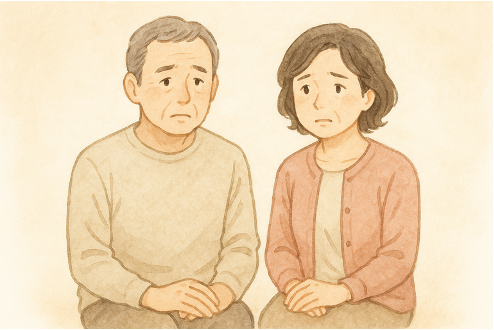
多くの方がまず感じるのは、
不安・戸惑い・恐れではないでしょうか。
──これから、どうなるんだろう。
──ちゃんと歩けなくなるの?
──薬を一生飲み続けるの…?
症状がまだ軽くても、「パーキンソン病」という言葉の重さに、心がふさぎ込んでしまう方も少なくありません。そして、ネットで調べれば調べるほど、不安が大きくなってしまった…という声もよく聞きます。
でも、どうか忘れないでください。
🌱 「治らない病気」=「何もできない病気」ではありません。
🌱 体のためにできることはたくさんあるのです。
このページでは、パーキンソン病の基本的な情報とともに、
すずらん薬局として大切にしている、“体の中から整えるサポート”の考え方をお伝えしています。
「これからどうすればいいのか分からない」
「薬だけに頼っていて大丈夫なのか心配」
そんな方こそ、ぜひ最後まで読んでみてください。
あなたが少しでも前向きに毎日を過ごせるように、
そのヒントがきっと見つかるはずです。
目次
どんな人がパーキンソン病にかかりやすいのか?
パーキンソン病は、中高年以降に多く見られる進行性の神経の病気です。
特に60歳以上の方に多く、加齢とともに発症リスクが高まることが知られています。
一方で、40〜50代で発症する「若年性パーキンソン病」も報告されており、年齢だけで判断できるものではありません。
また、家族内で発症するケースもありますが、遺伝的な要因が明らかな人はごく一部です。
現時点では、「この人がなりやすい」とはっきりした特徴はわかっていません。
パーキンソン病の症状
パーキンソン病は、脳内の神経伝達物質「ドーパミン」の減少によって、さまざまな運動機能や体の働きに影響が出る病気です。
症状の出方や進行のスピードには個人差があり、「どんな症状が出るのか」「どこに不調を感じるのか」は人によって異なります。
ここでは、パーキンソン病によって見られる代表的な症状についてご紹介します。
◆ 主な運動症状
パーキンソン病では、体を動かす機能に関係するさまざまな変化が現れます。以下はよく見られる主な運動症状です。
 安静時振戦(あんせいじしんせん)
安静時振戦(あんせいじしんせん)
体を動かしていないときやリラックスしているときに、自分の意思とはかかわりなく、手や足が小刻みに震える症状です。
- 筋固縮(きんこしゅく)
筋肉がこわばって、関節の動きがぎこちなくなる症状です。肩や首の強ばりとして感じる方も多く、動作がスムーズにいかなくなります。
- 無動・寡動(むどう・かどう)
動作がゆっくりになったり、動き出しに時間がかかったりする状態です。歩幅が狭くなったり、表情が乏しくなったりすることもあります。
- 姿勢保持障害(しせいほじしょうがい)
体のバランスを保つ力が弱くなり、転びやすくなります。体が前傾姿勢になったり、つまずきやすくなることがあります。
◆ 非運動症状について(自律神経の働きに関わるもの)
パーキンソン病は、「体が動かしにくくなる病気」というイメージが強いですが、実際には内臓の働きや睡眠、感覚、感情などにも影響が出ることがあり、それらは“非運動症状”と呼ばれます。
非運動症状が起こる背景には、「自律神経の乱れ」というような曖昧な表現ではなく、脳内の神経伝達物質であるドーパミンの減少が関係していることがわかっています。
ドーパミンは、運動を調整するだけでなく、視床下部や延髄など、自律神経の働きを調整する中枢部分にも作用しているため、ドーパミンが不足することで、交感神経・副交感神経の働きにも影響が出てくるのです。
- 便秘

腸の動きが鈍くなることで、排便がスムーズにいかなくなります。
これは、ドーパミンの減少によって副交感神経の働きが弱まり、消化機能が低下していることが原因の一つとされています。
- 発汗異常
汗が必要以上に出たり、逆にほとんどかかなくなったりすることがあります。
これは、交感神経の働きが不安定になっているために起こる症状の一つです。
- 起立性低血圧
立ち上がった時にめまいやふらつきを感じる状態です。血圧の調整も交感神経が担っているため、ドーパミンの減少により血圧のコントロールが難しくなることがあります。
- 排尿トラブル
頻尿や残尿感、尿が出にくいといった症状も出ることがあります。
これもまた、自律神経がうまく働かなくなることが原因です。
- 睡眠の質の低下
夜中に目が覚める、夢を見て体が動いてしまう(レム睡眠行動障害)などが報告されています。
睡眠リズムを調整する脳の中枢にも、ドーパミンは関与しています。
- 嗅覚の低下
匂いを感じにくくなることがあります。比較的早い段階で現れることもあります。
- 気分の落ち込み
やる気が出ない、気分が沈むといった変化を感じる方もいます。
ドーパミンは「やる気」や「快感」にも関わる神経伝達物質であるため、精神面にも影響が及ぶことがあります。
🧪 参考文献:Goldstein DS, et al.(2003)
パーキンソン病では、ドーパミン神経の変性とともに、自律神経(とくに交感神経)の機能が低下することが示されています。
このように、非運動症状もパーキンソン病の一部であり、脳内で起こっている変化が関係していることを理解することが大切です。
どれも「気のせい」ではなく、きちんと身体の中で起きている反応ですので、我慢せず、必要に応じてケアしていきましょう。
日常生活・生活上の注意
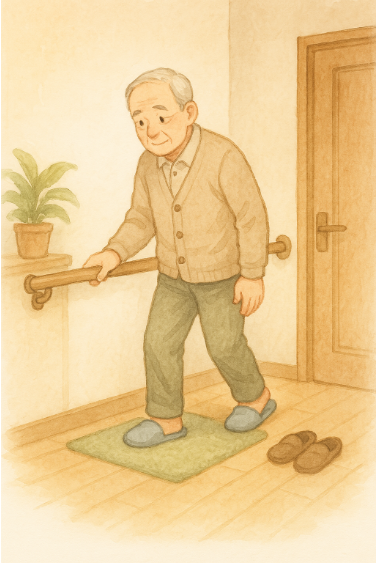
パーキンソン病と診断されたばかりのとき、「何か特別な生活をしないといけないのか
な?」「運動や食事はどうしたらいいの?」と不安になる方も多いかと思います。
でも、最初の段階では、日常生活を大きく変える必要はありません。
むしろ、今の生活の中で無理なくできることを意識していくことが大切です。
◆ 体を動かすことを自然に続ける
「動きにくくなる病気」と聞くと、体を動かすのが怖くなるかもしれませんが、軽い運動や
家事、散歩など、今の生活の中でできる範囲の動きを大切にしましょう。
動かさないことがかえって筋力低下や硬さにつながることもあります。
◆ 栄養バランスを意識してみる
パーキンソン病は、神経の働きをサポートする栄養が不足していると、体調が不安定になりやすいと考えられています。
今のうちから、たんぱく質や鉄分を意識した食事を心がけるだけでも、体を支える力は大きく変わります。
無理に食事制限をしたり、「○○はだめ」と決めつける必要はありません。食べられるものをしっかりとることが第一です。
◆ 気持ちを抱え込まないことも大切です
診断を受けたばかりのときは、「これからどうなるのだろう」と不安な気持ちがあって当然です。
大事なのは、一人で抱え込まずに、信頼できる人や場所に相談すること。
体のこと、薬のこと、食事のこと。
「こんなこと聞いていいのかな?」と思うようなことでも、気軽に相談できる場を持つことが、これからの生活の安心につながります。
パーキンソン病の治療法(現在一般的におこなわれている治療)
パーキンソン病の治療は、主に**「足りなくなったドーパミンを補う」「脳内の神経伝達の働きを整える」**ことを目的に行われます。
進行性の病気ではありますが、薬によって症状をコントロールできるケースも多く、日常生活を長く維持できる方もたくさんいらっしゃいます。
ここでは、現在一般的に行われている治療法についてご紹介します。
◆ 内服薬による治療が基本です
パーキンソン病の治療では、脳内のドーパミンを補うための薬が中心になります。
ドーパミンそのものを補う薬、ドーパミンの働きを助ける薬、またドーパミン以外の神経伝達に作用する薬など、複数の種類があります。
🔹 レボドパ製剤(L-ドーパ)
もっとも基本となる治療薬です。
体内でドーパミンに変換される薬で、不足しているドーパミンを直接補うことで、運動症状の改善が期待できます。
- ふるえ、筋固縮、動作の遅れなどに効果がある
- 長く使っていると、効き方に波が出る「オン・オフ現象」や、勝手に体が動いてしまう「ジスキネジア」などの副作用が出ることがあります
🔹 ドーパミンアゴニスト
脳内のドーパミン受容体に作用し、ドーパミンがあるかのように働いてくれる薬です。
比較的若い方や、治療初期に使われることが多いです。
- L-ドーパよりも作用はマイルド
- 吐き気や眠気、幻覚などの副作用に注意が必要です
🔹 MAO-B阻害薬、COMT阻害薬
ドーパミンを分解する酵素の働きを抑えることで、体内に残るドーパミンの量を増やす薬です。
他の薬と組み合わせて使われることが多く、治療効果を高める補助的な役割を果たします。
🔹 抗コリン薬、アマンタジンなど
一部の方に使用される薬で、ふるえの改善やジスキネジア(不随意運動)の抑制を目的として使われます。
副作用として認知機能の低下や眠気などが出る場合があり、高齢の方にはあまり使われないこともあります。
◆ 薬物治療だけでなく、リハビリや運動療法も
薬で症状を安定させることに加えて、日常的に体を動かすことも非常に大切です。
リハビリや軽い運動を取り入れることで、筋力や柔軟性を保ち、日常生活の質を維持する助けになります。
パーキンソン病の治療薬の副作用
パーキンソン病の治療では、症状をコントロールするために複数の薬が使われますが、その反面、長期的な服用による副作用が出てくることもあります。
ここでは、よく使われるお薬と、それに伴いやすい副作用についてご説明します。
◆ レボドパ製剤(L-ドーパ)の副作用
レボドパは、ドーパミンの材料となり、パーキンソン病治療の中核となる薬ですが、長期間使っていると効き方が不安定になることがあります。
🔹 オン・オフ現象
薬が効いている時間(オン)と、効き目が切れて動きにくくなる時間(オフ)が1日の中で繰り返されるようになります。
時間を見計らって薬を飲んでも、「今日はあまり効かないな…」という日が出てくることもあります。
🔹 ジスキネジア(不随意運動)
薬が効いているときに、手足や顔が自分の意思とは関係なく動いてしまう症状です。
鏡を見ないと本人が気づかないほど軽いこともありますが、日常生活に支障が出るほど強く出ることもあります。
◆ ドーパミンアゴニストの副作用
ドーパミンの受容体に直接作用する薬で、初期治療や若年発症の方によく使われます。
レボドパと比べて作用が穏やかですが、特有の副作用もあるため注意が必要です。
🔹 吐き気・眠気・立ちくらみ
飲み始めや増量時に起こりやすく、特に食後の眠気や集中力の低下を訴える方もいます。
🔹 幻覚・妄想
高齢の方に出やすい副作用のひとつで、現実にはない人や物が見える、誰かに監視されていると感じるなど、感覚や思考に変化が出ることがあります。
🔹 衝動制御障害
ごく一部の方に見られるもので、「買い物をやめられない」「ギャンブルにのめり込む」「過食になる」といった行動のコントロールが難しくなる副作用があります。
◆ MAO-B阻害薬・COMT阻害薬の副作用
これらは、ドーパミンを分解する酵素を抑えることで、体内に残るドーパミンの効果を高める薬です。
比較的副作用は少ないですが、他の薬と併用することでレボドパの副作用を強めてしまう場合もあります。
- めまい、ふらつき
- 吐き気、頭痛
- オン・オフ現象やジスキネジアの増強
などが出ることがあります。
◆ 薬の副作用とうまく付き合うために
副作用の出方は人によって異なります。
また、同じ薬でも体調や年齢、他に使っている薬によって感じ方が変わることもあります。
「この薬が合わないかも…」「最近ちょっと様子が変わった」など、気になることがあれば、
無理に我慢せず、主治医や薬剤師に相談することがとても大切です。

パーキンソン病はうつるのか?
パーキンソン病と診断されると、
「家族にうつったりしない?」「近くにいると感染するの?」と心配される方もいらっしゃいます。
結論から言うと、パーキンソン病は人から人へうつる病気ではありません。
◆ パーキンソン病は「神経変性疾患」です
パーキンソン病は、**脳の中でドーパミンをつくる神経細胞が徐々に減っていく「神経変性疾患」**の一つです。
感染症のようにウイルスや菌が原因で起こる病気ではないため、周囲の人にうつることはありません。
家族と同じ空間で過ごすことや、介助をすることに不安を感じる必要はありませんので、安心してください。
◆ 遺伝する可能性は?
多くのパーキンソン病は「孤発性(こはつせい)」といって、家族歴のない人に自然に起こるタイプです。
一部、遺伝的な背景が関与していると考えられるケースもありますが、それはごくわずかです。
ご家族の中で誰かがパーキンソン病になったとしても、それだけで他の家族の発症リスクが高くなるわけではありません。
◆ まわりの人が気をつけること
うつる心配はありませんが、パーキンソン病の方は、体が動きにくくなったり、転びやすくなったりするため、日常生活のちょっとしたサポートが必要になることがあります。
ご本人のペースに合わせて見守ること、焦らずゆっくり動ける環境を整えることが、安心して過ごすための支えになります。
パーキンソン病は治るのか?
パーキンソン病は、今の医学では“完治がむずかしい”とされる病気です。
そう聞くと、不安になってしまう方も多いと思います。
ですが、完治はできなくても、日々の暮らしを支えるために「できること」はたくさんあります。
薬の力を借りながら、少しでも快適に、そして自分らしく過ごすための方法は、きっと見つかります。
あれこれ難しく考えすぎずに、「できることから、少しずつ」やってみる。
それだけでも、これからの毎日が変わってくるかもしれません。
すずらん薬局での取り組み
パーキンソン病の治療では、主にドーパミンを補うお薬が使われています。
でも実は、「なぜ自分の体でドーパミンが作られなくなってしまったのか?」ということまで、詳しく確認していないのが現実です。
すずらん薬局では、そうした“体の根本的な状態”に注目しながら、薬だけに頼らないアプローチを行っています。
◆ ドーパミンを作れる体に近づけるために
パーキンソン病では、ドーパミンを作る神経細胞が弱っていきます。
でも、「ドーパミンを作る材料が足りていない」「脳に必要な栄養が届いていない」など、もっと根本的なことに原因の一端があることも多いのです。
たとえば──
- 食事の内容を見直して、神経の材料となるたんぱく質や栄養素をきちんと摂れるようにサポートしたり、
- 血液データや問診を通して、鉄分不足やエネルギー不足、脳への血流が足りていない状態をチェックしたり、
- 胃腸の働きが落ちている方には、きちんと栄養を吸収できるように消化のサポートを行うこともあります。
つまり、“その人の体が本当に必要な栄養を充分に受け取れる状態”になっているかまで見ていくのが、私たちの大事にしている視点です。
◆ 取り組みの一例
実際にご相談いただいた方には、こんな取り組みを行っています。
- 毎日の食事内容や体調の変化を伺いながら、栄養面・生活面を一緒に整えていく
- 鉄やビタミン、神経の修復に関わる栄養素が足りているかをチェックして補う
- 脳のエネルギー源をしっかり届けるため、血流やミトコンドリア機能の改善を図る
- 薬の副作用による胃の負担や食欲不振がある方には、胃の回復や吸収力を高めるケアを行う
- 心と体の状態に合わせた、無理のない継続方法をご提案する
その方の体調や生活に合わせて“ちょうどいいサポート”を一緒に考えていくのが、すずらん薬局のスタイルです。
◆ あなたに合った方法を一緒に探していきます
薬だけでは補えないこと、病院ではなかなか見てもらえないこと。
そんな“体の声”に耳を傾けながら、あなたに合った方法で、脳がしっかり働く環境を整えるお手伝いをしています。
「何をすればいいかわからない」
「今の治療だけでいいのか不安」
そんなときは、まずはお気軽にご相談ください。
すずらん薬局は、あなたの“今”の体に向き合いながら、未来の体づくりを一緒に考えていきます。

まとめ:今の体に向き合うことから始めてみませんか?
パーキンソン病は、完治がむずかしいと言われる病気です。
けれど、「治らない」=「何もできない」ではありません。
ドーパミンを補う薬は、今の体を支えてくれる大切な存在です。
でもそれと同時に、「なぜ自分の体でドーパミンが作れなくなってしまったのか?」という“根本の部分”にも目を向けてみることが、これからの生活にきっと役立ちます。
✔ 必要な栄養が足りていない
✔ 脳にしっかり血液が届いていない
✔ そもそも吸収力が落ちていて、栄養が体に入っていない
こうした体の状態は、人によって本当にさまざまです。
だからこそ、「この病気だからこの対策」という画一的な方法ではなく、あなたの体に合わせたサポートが必要なのです。
🌿 あなたの「今の体」を一緒に見つめてみませんか?
すずらん薬局では、食事・栄養・体調・心の状態まで丁寧にお聞きしながら、
あなたに合った方法をご提案しています。
「何をすればいいかわからない」
「薬だけでいいのか不安」
そんな気持ちを抱えている方こそ、ぜひ一度ご相談ください。
体の状態を整えることは、まだできることがたくさんあるという希望につながります。
あなたがこれからの毎日を少しでも安心して、前向きに過ごせるように──
すずらん薬局が、全力でお手伝いします😊